コンテンツ
- 日本語とやまとことば
- 区別されなかった同音の言葉
- 「かをり」と「にほひ」 - 言葉の成り立ち
- 「かをり」と「にほひ」 - 発音体感(語感)
- 平安期の人々にとっての「かをり」と「にほひ」
日本語とやまとことば
日本語は、普段あまり意識されませんが、非常に古い言語です。もちろん外来語や漢字を取り入れて変化してきましたが、その土台には「やまとことば」があります。
弥生時代あたりから似たような骨格の人々が、似たような生活習慣を重ねながら、何千年も培ってきた言語で、土地や風土、人々の身体感覚と深く結びついてきました。
学校で習った「訓読み」の多くが、このやまとことばに由来します。漢字が伝わる以前から、人々はひらがな表記に近い形で日常的に用いていたのです。

区別されなかった同音の言葉
やまとことばのおもしろさのひとつに、「同音異義語を区別しない」点があります。中西進氏の著書『ひらがなでよめばわかる日本語の不思議』ではこう語られています。
『鼻というのは、顔の真ん中に突き出ていて、呼吸をつかさどる重要な器官です。人間は呼吸することで生きているわけですから、鼻は生命活動のなかで最も優先的な命の根源、いわば“トップ”の存在です。そういうものが「はな」、植物の枝先に咲くのも「はな(花)」、そして岬の突端のことも「はな」といいます。すべて同じです。』
現代では「鼻」「花」「端」と漢字で書き分けますが、当時の人々にとっては同じ「はな」。響きそのものが意味を担っていたというのです。
さらに中西氏は、顔の感覚器官と植物の成長を結びつけています。
『「め」「はな」「みみ」と、ひらがなでよくよく見てみると、植物を連想できます。芽、花、実。目は芽が出る芽、鼻は花が咲く花と同じ音、耳は「実がなる」の「み」が二つ(頭の両側にありますね)。歯は葉と同じ音です。顔の中に植物の成長過程が表れているようです。
これは偶然に思えますが、古代人の自然観を映し出すものでしょう。芽が出て、花が咲き、葉が広がり、実を結ぶ。その成長プロセスと人間の顔を重ねていたのでしょう。』
「かをり」と「にほひ」 - 言葉の成り立ち
では漢字が輸入される以前、「香り」と「匂い」はどのような言葉で、どのようなニュアンスで理解されていたのでしょう。やまとことばでは、「香り」は「かをり」、「匂い」は「にほひ」と書きました。
- 「かをり(香り)」
「か」は「け」が変化したもので、「ぼんやり漂うもの」を意味しました。「をり」は酒が醸されるにつれて芳醇になること。合わせて「かをり」とは、漂い広がる芳醇な気配を指しました。のちに「香」の字があてられ、花や香木など雅で上品なものと結びつきます。 - 「にほひ(匂い)」
「に」は赤土を意味し、赤い色が顕れることを指しました。「に」が「ほ(秀)」として目立つ様子から「にほふ」という表現が生まれます。平安期の『源氏物語』では「梅がにほふ」といえば、香りと同時に花が鮮やかに咲く様を描いていました。やがて「におい」は漂ってくるものすべてに用い、香も顕著になれば「におう」というようになったのでした。
「かをり」は静かな気配としての芳香を、「にほひ」はもともと、光や色彩を伴って立ちのぼる生命の輝きを表しました。
「かをり」と「にほひ」 - 発音体感(語感)
次に、「かをり」と「にほひ」の違いを、昔の人がどう「体感していたか」、発音体感(語感)から探ってみたいと思います。
ところで、発音体感とは何?と思われる方もいらっしゃると思います。
詳しくは、黒川伊保子氏の著書「日本語はなぜ美しいのか」にある通りです。
『「キ」という音は、口腔内では、舌の中ほどを上顎に強く押し上げて、息を鋭く出すことで生まれる音。この「硬さ」と「尖り」が、身体感覚的に「鋭い突出」や「直進性」を感じさせる。この発音体感から、大地から硬く突出する「木」を表しました。また、「来」はこちらへまっすぐ向かう感じ。キリキリは尖った痛み、キンキンは耳をつんざく高音、キラキラは硬質な光。』
つまり「キ」は口腔内で生まれる鋭い緊張感のある音であり、それがそのまま「木」「来」といった言葉の原初的なイメージと結びついている、というわけで、これが発音体感です。
これを「かをり」と「にほひ」にあてはめてみます。
「かをり」
- 「か」=硬く澄んだ音で始まり
- 「を」今とは違い音が「wo」だったので、ふわっと息を伴い漂う・広がる気配。
- 「り」=軽やかで繊細なラ行
→ 音の流れとしては、静かに広がり、余韻を残す上品な雰囲気。
「にほひ」
- 「に」=鼻に抜けるやわらかさ
- 「ほ」=息が吐き出され、温かく広がる
- 「ひ(hi)」からは光・火の鋭さも連想され、生命感や強い存在感。
→音の連続としては、ふくらみ、鮮やかに立ち上がる生命感のある雰囲気。

平安期の人々にとっての「かをり」と「にほひ」
「かをり」は、香木や花の香りが「静かに漂う」イメージがあり、上品で洗練された感覚、仏教的な「香」の観念にもつながるもの。いわば「気配としての香」のようなものだったと思われます。
一方、「にほひ」は、光と色彩を帯びながら「立ちのぼる」イメージがあり、生命の輝き・美しさ・艶やかさを表すもの。単なる香気でなく「存在感そのものの放射」のようなものだったと思われます。
このように、言葉の成り立ち、ニュアンス、発音体感(語感)から、「かをり」と「にほひ」の違いが見えてくると、かの紫式部が源氏物語で「薫」と「匂宮」を、対比するように登場させた理由がわかる気がします。
「薫」は嗅覚的に、内面的に、静かな余韻が続くような魅力があり、生まれつき芳香が漂う人物として描かれます。一方、「匂宮」は視覚的に、表層的に、華やかな魅力があり、競うように香を纏う人物として描かれます。
そして、一般的な研究では、紫式部は、長続きする内面的な魅力を重んじて、「薫」に価値を見い出していると言われています。(結果的にはどちらも女性たちを幸せにできない男性像として描かれましたが・・・)
紫式部がでてきたからには、「紫の上」についても考えてみたいと思うのですが、長くなりそうですので、続きは後編にまとめました。そちらも是非ご覧ください。
よろしければ以下のブログ記事もご覧ください。
パルファンサトリの 「 紫の上 」 リニューアル
ニックネーム:T.T
プロフィール:香水ソムリエ。パルファンサトリ フレグランススクールにてインストラクターをさせていただいていました。現在はアトリエで接客を担当しております。


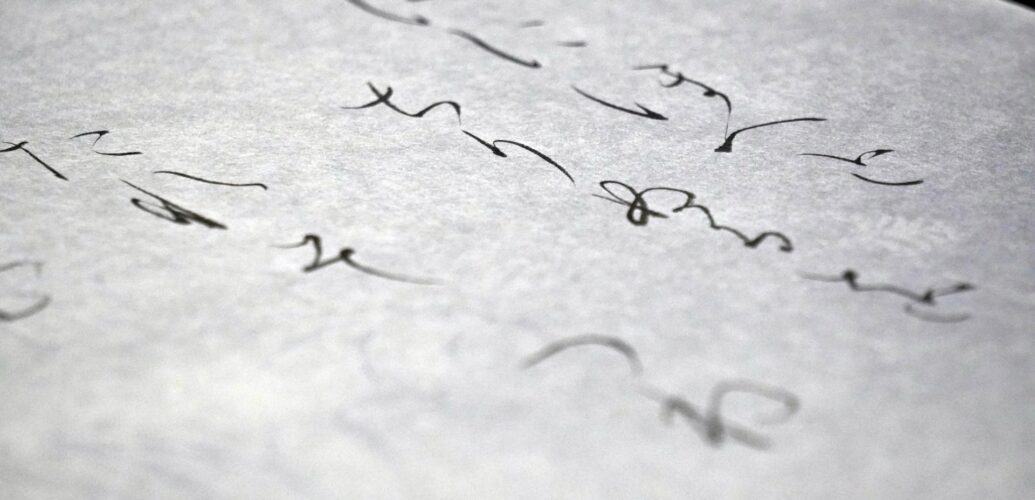

の木の巨大な花のクローズアップ(HANAHIRAKU-ハナヒラク-の着想-150x150.jpg)


