陰翳(いんえい)と絢爛 (けんらん)
「美というものは常に生活の実際から発達するもので、 暗い部屋に住むことを余儀なくされたわれわれの先祖は、 いつしか陰翳の内に美を発見し、やがては美の目的に沿うように陰翳を利用するに至った」 ── 谷崎潤一郎『陰翳礼讃』
陽の光に目を細めた 正午、お寺の境内にふと足を止めました。
そこには一輪の牡丹が咲いていました。
まばゆさの中にありながら、どこか涼しげなその姿。 咲き誇るというよりも、静かに座している。まるで、そこに居ること自体が役割であるかのような。
花を引き立てていたのは、意外にも陽射しではなく陰です。
幾重にも重なる花びらがつくる薄暗がり、葉の影が映す淡い濃淡。
そう、光の美しさは影の存在によって際立つのだと、あらためて思い知らされたのです。
陰翳という美学
作家・谷崎潤一郎が書いた『陰翳礼讃』という随筆があります。 その中で彼は、明るさ一辺倒の西洋の照明文化に対し、日本の美がいかに「影の中」に生まれていたかを語ります。
金箔の屏風も、漆器の艶も、仄暗い室内にあるからこそ、その輝きが生きるのだと。
たとえば、障子を通して差し込む午後の光。
直接的ではないその明るさに、わたしたちはどこか安らぎを感じます。
すべてを照らし出すのではなく、あえて見えない部分を残す。
その「余白」の中にこそ、想像の余地と、美しさが生まれるのです。
谷崎はこう記しました。
「美というものは常に生活の実際から発達するもので、 暗い部屋に住むことを余儀なくされたわれわれの先祖は、 いつしか陰翳の内に美を発見し、やがては美の目的に沿うように陰翳を利用するに至った」。

絢爛を映す陰翳
「絢爛」という言葉には、華やかさの奥に、どこか退廃の影が漂います。
それは、単なる豪奢ではなく、ひとつの極みに達したがゆえに生まれる、静かな崩壊の気配。 繁栄の頂点であればあるほど、その美は陰影を必要とするのです。
あらゆる色が一様に照らし出された場所では、絢爛はただの装飾にすぎません。
しかし、仄暗い室内や、あるいは暮れなずむ時刻の中にあってこそ、そこに命が吹き込まれる。 漆黒の背景があるからこそ、金はいっそうまばゆく輝くのです。
日本の美は決して“見せる”ことだけを目的としてきませんでした。
むしろ、“隠す”ことで、想像を喚起し、奥行きを与えてきた。 障子越しの光、にじむ輪郭、ほのめく気配──それらは、すべて陰翳の中にあって絢爛を際立たせるものだったのです。
牡丹が宿す陰翳
牡丹の美しさは、陰翳の中にこそ宿る。
明るさは輪郭ではなく、幾重にも重なる花びらの奥にたたえられています。
昼には、障子越しの柔らかな光が、白い鳥の子の襖に反射し、床の間をほのかな明るみに包む。
夜には、仄暗がりの燭台に照らされ、ただ一輪が浮かびあがる。
陰翳は光に従うのではなく、光を引き寄せて存在を増す──その逆転の瞬間に、牡丹は最も深い姿を見せるのです。

牡丹という花は、一見、シャクヤクによく似ています。
けれど香りを嗅げば、その違いは明らかです。
シャクヤクの澄んだ香りに対して、牡丹の香りは──ひどく青くさく、決して「いいにおい」とは言えません。
座敷に生けるなら、草牡丹ではなく、花弁を幾重にも重ねた、中央に金色の蕊を湛えたものがふさわしい。
それは、花というよりも「鑑賞のための華」。
念入りに整えられ、重厚で、視線を受け止めるために存在しているような、そんな牡丹です。
ある日、明暗の狭間にあるような柔らかな明度の中で、満開の牡丹の花びらが、ぱさっと音もなく、重なって散り落ちました。
せいいっぱいに咲ききったその花は、自分自身の重さを、ついに支えきれなくなったように。
あるいは──注がれた視線の重さに、耐えかねたのかもしれませんでした。
人の動きに誘われ、空気がわずかに揺れると、香りがふわりとほどけていく。
残されたかすかな気配に、記憶の奥がふと揺さぶられることもあるでしょう。
すべてを明かさないこと。すべてを語らないこと。
その余白のなかにこそ、香りは長く息づき、美は生まれるのです。

永井聡の牡丹 ─ 絵に宿る気配
この牡丹の作者は、絵師の永井聡さん。
和の空間に関わる人ならば、どこかで必ず永井さんの仕事に出会っているはずです。
明治記念館「金鶏の間」、旧御用邸の装飾、銀座のラグジュアリーブランドの店舗内装── それらの背後には、確かに永井さんの手がある。
本人は表に出ることなく、名を語ることもほとんどありません。
しかし、和紙と箔、砂子を専門とし、伝統工芸士として確かな技を積み重ねてきた職人であり、絵師です。
だからこそ、永井さんに描いていただいた牡丹は、ただ一輪を切り取った絵ではありません。
背景には、かすかに浮かび上がる葉が配され、空間全体に奥行きを与えています。
その深さがあるからこそ、花びら一枚一枚が陰翳の中からふわりと浮かびあがり、ひそやかな輝きを帯びていく。
光と影が呼応することで、牡丹の絢爛さは際立ちながらも、決して騒がしくならないのです。
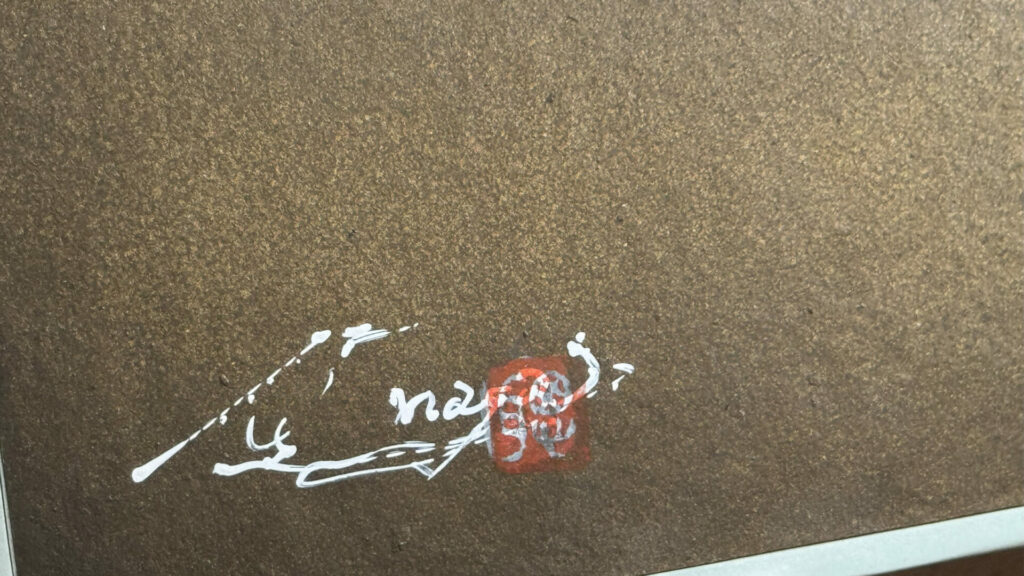
工房での出会い
私が初めて永井さんの作品を見たのは20年ほど前のこと。 ひと目で心を奪われ、気づけば工房に何度も通うようになっていました。 砂子を施した和紙の、あの静かな煌めき──七夕の唱歌「金銀砂子(きんぎんすなご)」の意味を知ったのもこの時です。 描き散らかした下絵や、用途の定まらない和紙を「これ、いいですか?」とお願いしては、宝物のように持ち帰った日のことを、今でもよく覚えています。
香りと紙が重なるところ
パルファンサトリの香水ボトルの背景に映っている和紙も、すべて永井さんの手によるもの。
光を浴びたときにだけ、そっと現れる微光の粒子。
香りもまた、そんなふうに漂ってほしいと、私は思っています。
そして今回、新しい香水のイメージをもとに、永井さんに特別な牡丹を描いていただきました。
それは、絢爛でありながらも派手すぎず、余白に気配をとどめる一幅。
香りと絵が、静かに重なろうとしています。
お披露目はもうすぐ。
けれど、すべてが見えてしまう前の、このわずかな時間こそ、もっとも美しいのかもしれません。
参考
- 資料・参考文献(記事末尾にまとめる形)
- 谷崎潤一郎『陰翳礼讃』中央公論新社〈中公文庫〉, 1975年(初版1933年)
- 京都市「文化史10 銀閣寺(慈照寺)」京都市公式サイト
https://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/rekishi/fm/nenpyou/htmlsheet/bunka10.html - 「銀閣における観月のシークエンシャル・シミュレーション」日本デザイン学会研究発表大会概要集, 2003年
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jssd/50/0/50_0_85/_article/-char/ja - 「慈照寺」Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%88%E7%85%A7%E5%AF%BA
大沢さとり
パルファン サトリ 創業者・調香師。
香りにまつわる素材や香水の制作背景を、少しずつお届けしています。
高雅な梅の香りの背景は永井氏の絵と和紙です
N工房の永井氏を訪問したときの記事です



の木の巨大な花のクローズアップ(HANAHIRAKU-ハナヒラク-の着想-150x150.jpg)


